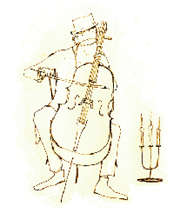
p r o f i l e
|
冬の頃にはポプラの並木の道も、 音もなくしんしんと、両袖の田んぼと真っ白にひとつになる所に、 4人のおじさんたちは住んでいます。 春にはふきのとうを摘み、菜の花に埋もれて歩き、桜を見上げます。 夏には蝉の声に耳を澄まし、河原を散策して線香花火で遊びます。 秋には山の細い道をしずしずと行き、冬ごもりの準備を始め、 冬には音のない景色に寄り添い、暖炉の火を絶やしません。 こうして4人のおじさんたちは、4つの季節と共に暮らしています。 |
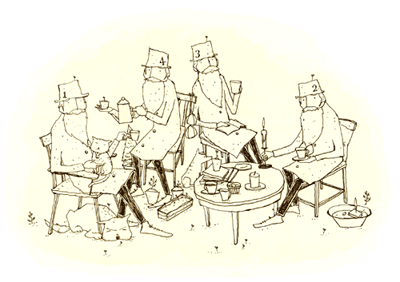
|
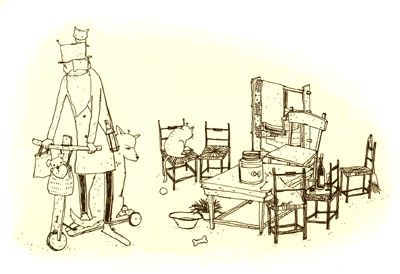
|
1番目のおじさんは動物と暮らすおじさん。 お天気の良い日には、動物たちのお布団をお日さまにあて、 みんな揃って朝のお散歩に出かけます。 夕ご飯の前には、ご近所のご機嫌伺いをしながら歩きます。 ご近所では、みんなの好きなおやつを用意して待っていてくれます。 お礼の品は、動物の毛で作ったフェルト玉で、 フェルト玉はあんまり役には立ちませんが、 もらった人は皆にこにこするので、それでいいと1番目のおじさんは思っています。 夜は動物語の辞書の執筆という大事なお仕事があります。 1番目のおじさんは、多くの動物の言葉がわかるから。 でも大切なのは言葉ばかりではありません。 以前遠くに住むワニが、ホロホロ泣きながらやって来ました。 1番目のおじさんは「お茶でもいかがですか?」というワニ語しか知らなかったのですが、 一緒に座っていいこいいこしているうちに、 ホロホロワニが「あごの下にトゲが刺さって痛いです」と言いたいのがわかりました。 言葉が違っても解りあえることもあるってことです。 |
|
2番目のおじさんは火を灯すおじさん。 大昔から人は火の傍らで暮らしてきました。 キャンドルの灯りは、いつものお茶の時間を、 ちょっと上等なお茶の時間にしてくれます。 暖炉の灯りは、家を橙色に包み、美味しい匂いを香らせたりしてくれます。 キャンプファイアの灯りは、 それを囲む人たちと、見えない握手をすることができます。 2番目のおじさんは、今そこに共に生きている植物や動物が、 1枚の大きなキルトで包まれるよう、みんなの灯りを用意しています。 日が暮れる頃には、「キャンドルをどうぞ。」と、家々をノックします。 皆が寝静まる頃には、「火の用心...」と、家々をノックします。 2番目のおじさんのこのノックで、皆は眠りにつくのです。 そして2番目のおじさんは、たった1人夜更かししながら、キャンドルの灯りを見ています。 しんしんとした夜更けに、1軒だけ小さな灯りのついている窓があったら、 それが2番目のおじさんのおうちです。 |
 |
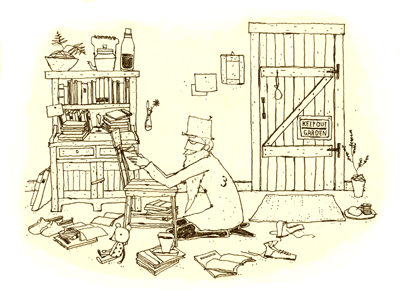 |
3番目のおじさんは本を読むおじさん。 どこへ行くにも何をするにも、本を片時も手放すことはありません。 3つ隣の町のカワウソと、6つ隣の町のカワウソの好物の違いも知ってますし、 美味しいセロリの見分け方も知っています。 どうしてソラリスの映画に、日本の首都高が登場したのかも知ってますし、 方程式の美しい解き方も教えてくれます。 コンタクトレンズの入れ方のコツだって教えてくれます。 口内炎には、ナスのへたを黒く焼いたものを塗るといいとか、 乗り物酔いには、おへそに梅干し貼るといいとかも知っています。 夏みかんのジャムの美味しいつくり方、香りの良い薫製の作り方、 臭い消しのハーブ、月桂樹のリースの作り方も教えてくれます。 ネパールの友達にお手紙を出す時にも、良い塩梅に訳してくれますし、 日の出日の入りの時刻から、今日のラッキーカラーだって万全です。 何か知りたい時、ちょっと困った時など、 皆が3番目のおじさんのところへまず出かけて行くのは、こんな理由があるのです。 |
|
4番目のおじさんは種を蒔くおじさん。 4番目のおじさんの蒔いた種は、不思議とすくすくと育ちます。 葉っぱの緑は深い力に溢れ、お花の色は可憐で、ことさら良い香りです。 種を入れた柔らかい布の袋をいつも携帯し、ここぞと思った所に種を蒔きます。 木の床だろうと、猫の頭だろうと、他のおじさんの帽子だろうと、おかましなし。 でもこっそり伸びた芽は、それはそれは可愛らしいものなので、 皆、知らず知らずのうちに、その芽を大事に思ってしまいます。 背中に芽が出てきたりすると、眠る姿勢にちょっと苦労したりする時もありますがね。 4番目のおじさんは、お日さまと共に寝起きしているので、 おじさんたちの夜の会合では、居眠りしてしまうこともよくあります。 種を蒔く旅にも時折出かけるので、留守のことも多いです。 そんな時には、他のおじさんたちが、 4番目のおじさんの芽に、お水をやりに回ります。 そしてお土産を楽しみに、4番目のおじさんの帰りを待つのです。 |
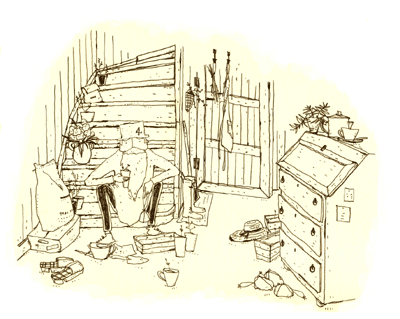 |
:card-ya home